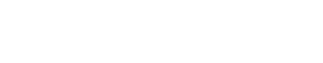With You 乳がんの現状、正しく知って
公明新聞に「伊藤たかえ」の記事が掲載されました。
■発症のピークは閉経後/肥満がリスクの要因に
公明党の皆さまには、乳房再建手術への保険適用や、乳がんの検診無料クーポン配布など、女性の健康サポートに尽力してきたことに対し心から感謝申し上げます。
私は現在、3児の母として、また子育て中のがん患者支援のNPO活動などを通じ、医療や福祉の課題に取り組んでおります。この春には、九州大学を離れ、さくらウェルネスクリニックを開業しました。
それは、私自身、乳腺外科医として、医療の現場やNPO活動を通じて、多くの乳がん患者のお母さんたちと出会い、別れを経験してきたからです。幼い子を残して亡くなるお母さん、経済的な問題などから家族関係がこじれるご家庭、ひとり親家庭で治療と子育ての両立に苦しむ方々。こうした現実に直面し、「何かできることを」という思いから、早期発見・早期治療だけでなく、がんの発症予防にも取り組んでいます。
■乳がんの現状
日本の乳がんの現状についてお話しします。私が医師になった20年前は17~18人に1人が罹患していましたが、現在では女性の9人に1人が乳がんになる時代になってしまいました。これは、20年前に欧米が8人に1人といわれていた発症率に迫る勢いです。
乳がんは世界的に見ても、女性で最も罹患数の多いがんです。2020年は世界全体で新たにがんと診断された罹患数では、乳がんが肺がんを上回り、最も多いがんとなりました(11.7%)。日本国内では、新たに診断される方が毎年約10万人に達しています。
発症のピークも変化しています。以前は40代後半でしたが、現代では閉経後の60代から70代に、それを上回る大きなピークができています。閉経後の大きなピークが形成された一つの要因に、「肥満傾向」があるといわれています。現代は「飽食の時代」であり、女性はバイオリズムの中で閉経を迎えると脂肪を蓄積しやすくなります。この時期に生活を見直さないと、乳がんのリスクが高まってしまいます。
ですので、乳がんは若い人の病気という認識を改めて、30代後半から80代までの長期にわたり、向き合っていく必要があります。
■マンモグラフィー検診/「痛みへの配慮」全国へ
■検診の現状
乳がん検診の受診率は、米国やイギリスなどの欧米が70%を超えているのに対し、日本では40%台にとどまっている現状があります。この大きな原因の一つは、「マンモグラフィーは痛い」という先入観です。しかし、生理前や授乳期を除き、必ずしも誰もが痛いわけではありません。
検査中に体を真っすぐに立て、リラックスし、力を抜いて受けることで痛みは軽減されます。我慢せず、痛い時は技師に伝えていただければ配慮が可能です。
また、マンモグラフィーは、ステージ0期のサインである、しこりになる前の「石灰化」した微細な乳がんを見つけるのに非常に有用な検査であり、早期発見に欠かせません。
■検診の課題
一方で、日本人の多くは乳腺濃度が高く、マンモグラフィーだけで小さな「しこり」を見つけるのが難しいという課題があります。これを解決するため、40代の高濃度乳腺の方を対象にマンモグラフィーにエコー(超音波)を併用する研究が行われました。その結果、マンモグラフィー単独での感度が77%だったのに対し、エコー併用では91%に向上し、ステージ0、1期の早期症例が7割を超えました。
今後、エコー検査の併用が死亡率の改善に寄与するという結果が得られた際には、例えば、乳腺濃度が高い方を対象としたエコーの併用を、ぜひ皆さまのお力で実現していただきたい。
これからの乳がん検診は、痛み軽減機能付きのマンモグラフィー(乳房圧迫完了後に厚みが変化しない範囲で減圧を行って痛みを軽減する)の導入や、痛みに配慮した撮影技術の教育など、「痛みへの配慮」を全国に広げることが重要です。
また、早期発見の精度向上と、経済的に持続可能であること、そして検診を通じて不安の軽減につながることが大切です。それが日本の女性とご家族から乳がんによる悲嘆をなくす道だと信じております。
引き続き、社会に安心と健康を届ける政治の実現を心より願っています。