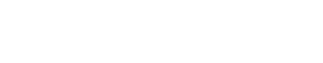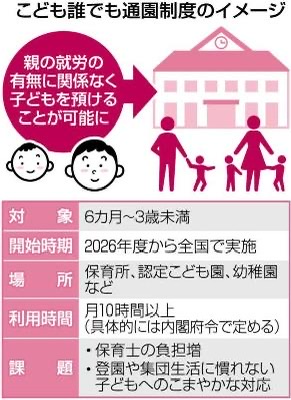養育費、離婚後の未払い防止へ
公明新聞に「伊藤たかえ」の記事が掲載されました。
合意なくても 一定額の請求可能に
党部会に法務省が省令案提示
離婚後に父母間の取り決めがなくても別居親に一定額の支払いを義務付ける「法定養育費」について、法務省が子ども1人当たり月額2万円とする省令案をまとめた。2026年5月までに施行される改正民法に基づく制度で、未払いを防ぐ狙いがある。28日、公明党法務部会が衆院第1議員会館で開いた会議で、同省が案を示した。

小泉龍司法相(当時、左端)に提言する伊藤孝江氏(右から2人目)ら=2024年2月29日 法務省
養育費の支払いは民法上の義務で、金額は収入などにより個別に算定する。厚生労働省が21年に行った調査では、養育費を受け取っているのは母子世帯で28.1%、父子世帯で8.7%にとどまり、ひとり親世帯が困窮する一因となっている。
昨年5月に成立した改正民法では、離婚時に事前の合意がなくても法定養育費を請求できる仕組みを新設。省令案は「子の最低限度の生活を維持する標準的な費用」を基準に、月額2万円と設定した。離婚後も父母双方が子の親権を持つ「共同親権」制度の導入と合わせ、子どもの養育責任を果たせるようにする。
一方、養育費の未払いがあった場合は、支払義務者の財産を差し押さえて取り立てることができる仕組みも整備。他の債権者より優先して弁済を受けられる「先取特権」(優先権)が付与され、上限は子ども1人当たり月額8万円とした。
法務省は9月からパブリックコメント(意見公募)を行い、具体的な内容を詰めるとともに、施行後も必要に応じて見直しを図る方針だ。
「子の利益」を最優先
法定養育費を巡っては、党法務部会が昨年2月に行った政府提言の中で、子どもの利益を最優先にする観点から、速やかな創設を主張。国会質問などを通じて、支払いが滞った場合の執行手続きの援助など一貫してサポートする体制構築を訴えていた。
子どもを切れ目なくサポート
党法務副部会長 伊藤孝江 参院議員
家族のあり方が多様化する中、毎年、十数万人の子どもが父母の離婚に直面している。離婚後、一部の父母間で取り決めができず、養育費を受け取ることができない現実がある。こうした背景を踏まえ、公明党は一貫して法定養育費制度の創設を提唱してきた。
別居親でも子どもの親であることは変わらず、養育責任を持つことが重要だ。子どもが生活する上で、切れ目のない経済的支援を講じるため、党としても制度の周知を図るなど政府の取り組みを後押ししていく。